札幌最古の霊場 妙見山本龍寺

札幌市東区の環状通東駅からほど近い場所に、開拓が始まった頃からこの地を見守り続けているお寺があるのをご存じでしょうか。
その名を「妙見山本龍寺」といい、起源は江戸時代末期の慶応3(1867)年まで遡ります。
この記事では、「札幌最古の霊場」として知られる妙見山本龍寺の歴史と見どころをご紹介します。
本龍寺の起源と歴史
妙見堂の建立:開拓との深い関わり
妙見山本龍寺の始まりは、慶応3(1867)年に大友亀太郎によって建立された妙見堂にさかのぼります。
前年に江戸幕府から石狩地方の開拓を命じられた大友亀太郎は、この地に御手作場(開拓農場)を開設する際、集落の守り神として妙見菩薩像を祀る妙見堂を建立しました。

興味深いのは、この妙見菩薩像にまつわる言い伝えです。
開拓判官・島義勇が所持していたこの菩薩像は、眼病を患い失明の危機にあった大友亀太郎に授けられました。
亀太郎が一心に祈願したところ、その霊験によって病気から回復し盲目を免れたため、感謝の気持ちを込めて妙見堂を建立したというのです。

ただし、史実を検証すると、島判官の開拓判官在任期間は明治2(1869)年7月から翌年1月と、妙見堂の建立より2年ほど後のことです。
また、大友亀太郎は明治2(1869)年10月に御手作場を開拓使に引き渡し、翌年6月には北海道を離れています。
これらの事実から推測すると、妙見菩薩像は大友亀太郎自身が奉持していたもので、島判官は妙見堂建立に直接関わっていない可能性が高いと考えられます。
妙見堂から本龍寺へ:正式な寺院となる
大友亀太郎が明治3(1870)年に北海道を離れた翌年、妙見堂は増築され、開拓使の許可を得て休泊所を称するようになりました。
そして明治14(1881)年、宝珠山金龍寺(石狩市)の末寺である妙見山本龍寺として公認されるに至ります(宗派は日蓮宗)。

なお、札幌市西区の日登寺は明治9(1876)年に加藤清正像を祀って創建されましたが、その際、妙見堂の建物を移築して参詣堂にしたと伝えられています。
札幌最古の寺院の伝統:妙見尊大祭
妙見堂は開拓時に集落の鎮守として建立されたこともあり、産土神的な存在でもありました。
そのため、毎年8月に行われる妙見堂のお祭り「妙見尊大祭」は、様々な催しが繰り広げられる「村の鎮守のお祭り」として大いに賑わいました。
札幌市内の寺院の祭りでは最も古い歴史を持つ妙見尊大祭ですが、現在は毎年7月に「妙見尊御縁日正当祈願祈祷会」として執り行われています。
本龍寺を訪ねて

「札幌開拓産土の妙見様」「眼病・癌封じのお守りと絵馬」といった案内が書かれた、境内北側の門。
傍らには「札幌最古之霊場」の碑もあり、本龍寺の由緒を物語っています。
この門から境内へ入ってすぐ右手の建物2階が本堂です。
この日は秋のお彼岸の時期ということもあり、境内にはお墓参りの方の車が多く停まっていました。
妙見堂:開拓の精神が宿る本龍寺の原点

まずは本龍寺の原点である妙見菩薩像を祀る妙見堂を参拝します。
お堂には、3期にわたって北海道知事を務めた堂垣内尚弘氏の筆による「開拓妙見山」の扁額が掲げられています。


妙見堂を守るのは、昭和14(1939)年に奉納された一対の狛犬です。
『札幌村史』によると本龍寺は同年に堂宇を改築したとあるので、それを機に奉納されたものでしょうか。
狛犬をお寺で見かけるのは珍しいですが、これは妙見堂が村の鎮守として深く信仰されていたことの表れのように思えます。
札幌村創建百年碑:郷土の歴史を刻む記念碑

札幌村は昭和30年に札幌市と合併するまで存在した村で、その区域は現在の札幌市東区とほぼ同じでした。
その開拓は、慶応2年(1866年)の大友亀太郎による御手作場の開設に始まりますが、それから100年を迎えた昭和41(1966)年に建てられたのが、この札幌村創建百年碑です。
現在は本龍寺の塀に割り込むような形で設置されていますが、文献によると1980年代後半頃は妙見堂の手前に建てられていたようです。
境内に残る歴史の痕跡:多彩な石碑群
「福聚海無量門」の扁額が掲げられた境内東側の山門の左右には4基の石碑が並んでいます。

山門に向かって右手には、「馬頭観世音」碑と「南無妙法蓮華経 日蓮大菩薩」碑の2基。
このうち「日蓮大菩薩」碑は明治時代に建てられたものです。

左には「島判官守護神 札幌妙見尊霊靈場」碑と「開拓信仰 幕吏大友翁史跡」碑と、本龍寺の起源を物語る2基の石碑が並んでいます。

境内北側にはもう1基、馬頭観世音碑があり、こちらは小ぶりながら馬頭観音の石仏と共に小さなお堂に祀られています。
一般的に馬頭観世音碑は、馬の無病息災祈願や慰霊のために建てられます。
純農村として発展したかつての札幌村において、馬は農業に欠かせない労働力として、ごく身近な存在だったことでしょう。
開拓の記憶を受け継ぐ札幌最古の霊場

札幌開拓の礎を築いた大友亀太郎によって建立された札幌最古の寺院、妙見山本龍寺。
その起源となった妙見堂は、開拓期の人々の精神的な支えとなり、厳しい環境での生活を乗り越える大きな力となってきました。
本龍寺の近隣には札幌村郷土記念館や大友公園など、札幌の郷土史に触れられるスポットが点在しています。
これらと合わせて参詣することで、より深く札幌の開拓史を感じることができるでしょう。
ぜひ、歴史の息吹を感じる旅に出かけてみてはいかがでしょうか。
アクセス
こちらもおすすめ

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。


🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。
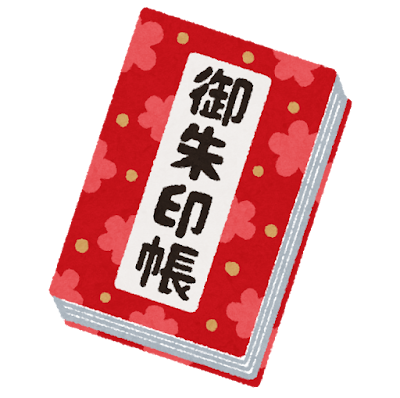

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4be719c5.80cb071b.4be719c6.c602378f/?me_id=1270375&item_id=10000073&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhotokudo%2Fcabinet%2Fnokyotyo%2Fsyuinntyo3%2Fapd004-3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


